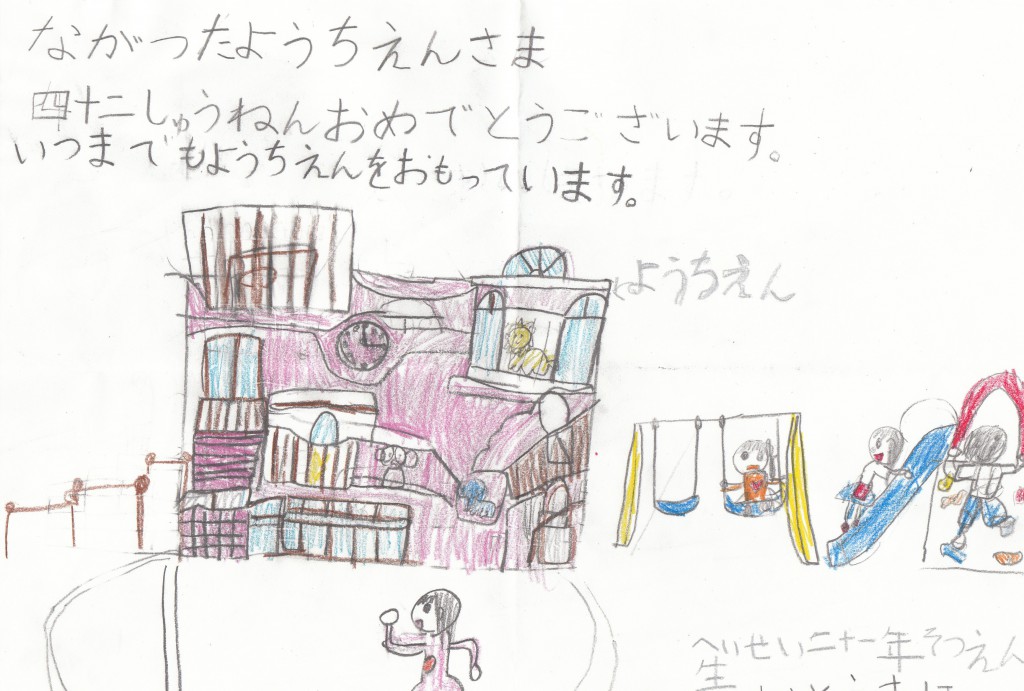< 今日は鳥です。 >
困った時は鳥ですが、土曜日に新年1月に私が担当する
「子ども探鳥会」の下見に行ってきました。
日差しがたっぷりで、気持ちの良い1日でしたね。
お弁当まで持って行って、他2名のスタッフとあれや
これやとプランを立ててきましたが、
あっ、場所は大和市の 泉の森 と言います。
よろしければ参加されませんか?ゲームもやりますよ。
ここは鳥の種類も多く、とても楽しめるところです。
土曜日はたくさんのカメラマンがお目当ての鳥を狙っていました。
カメラマンさんたちは年配の男性が多く、私のような若い!?女性には
優しく出ている鳥を教えてくれるのですが、狭い場所で三脚を立てていると、
他の方々(散歩の人や通行人)に迷惑ですし、何より鳥たちにもストレスを与えますので、
チラッと見てすぐに遠慮します。あまりそばに居るとおじ様たちの醸し出す香りにも引き気味になりますので・・・・・・。
そこで狙っていた鳥はこれ。

数万羽がロシアの北東部から越冬にわたって来ますが、
その群れの中にちょっと変わったツグミがいるのでしょう。
泉の森にはざっと100羽~150羽はいたでしょうか。
あっ、そうそう、この鳥は 「ツグミ」 といいます。
一昔前は、たくさんの数が日本に渡って来るので、
カスミ網を掛けて、一網打尽に捕獲し、焼き鳥にされていました。
もちろん今は禁止です。信じられませんね。
大きな大きなレンズを構えて、じっと待つ事数時間。
私は別の鳥を狙っている方に場所を譲ってもらいましたが、
時間が無く待ってられず、1時間余りで引き上げてきました。
ですから写真は無し。
私の撮りたかったのは、「ルリビタキ」 と言います。
青とオレンジのきれいな鳥です。
スズメよりちょっと小さく、目がくりくりです。
こちらは漂鳥と言って、日本国内を移動している
鳥です。もちろん大陸から渡って来る個体もいますが、
国内で標高の高い所から、低い所へ冬場は
降りてくるのです。
オスはとてもきれいです。メスも優しいオリーブ色と
薄い黄色が入ります。
素敵でしょう。
どこかで写真が撮れたら、ご紹介しましょう。
最後に 「ツグミ」 の仲間でこんな鳥もご覧下さい。
赤と白です。
いい写真とは言えませんが、これは赤い方の アカハラ。
そして 
白い方の シロハラ です。 同じツグミの仲間で、お腹が赤いのと白いのがいます。
さて、どちらが気が強いでしょうか?
気になる方は、いまお山でこの2羽がなわばり争いをしていますから
見に来て下さい。といっても早朝ですが・・・・・・・・。